LABORATORY熱の実験室
- ホーム
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
- 第10回 実験レポート
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
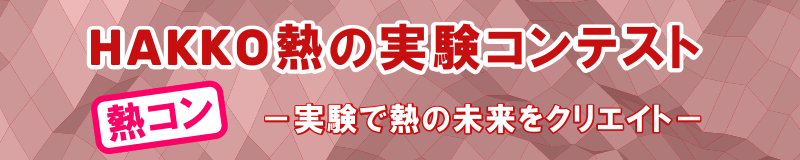
■ 「第10回 八光熱の実験コンテスト」 実験レポート
| 連番 | 所属 (応募時点) | 実験メンバー (チーム名) ◎は代表者 |
| 実験タイトル | ||
| 実験レポート(説明は実験企画時の内容) | ||
| 所属50音順・敬称略 | ||
| 1 | 秋田県立由利工業高等学校 環境システム科 |
◎武田 智樹、横山 雄一、横手 裕也、畑 凌我 (水で世界を救おう!班) |
| 色と素材と太陽と空気を活用して水を蒸留・温水化! (色+素材)×太陽+空気=きれいな水で世界を救おう! | ||
|
|
||
| 太陽エネルギーを使った水の蒸留と温水化システムの構築をめざしている。注目したのは、ソーラークッカー、蒸留装置、プールの水と海水である。特にソーラークッカーは、ライフラインの普及が不十分な国や地域で当たり前のように利用されていて、泥水をソーラークッカーで沸騰させたものをそのまま飲用する国や地域があると聞いている。ソーラークッカーに単蒸留の原理を組み合わせることで泥水をきれいにできる!と考えた。 | ||
| 2 | 茨城大学 工学部 機械工学科 茨城大学大学院 理工学研究科 機械工学専攻 松村研究室 |
◎長津 健吾、富山 あゆみ、玉根 正貴 |
| 熱源を追尾して自動運転に挑戦してみよう!! | ||
|
|
||
| 自動運転実現のための情報として、直接目に見えない"熱源"に注目し、検知の方法として赤外線カメラに焦点を絞った。撮影した赤外線画像をリアルタイムで動画処理する手法を確立し、熱源検知のための赤外線カメラを搭載した自立型ロボットカーを製作して、暗闇でも自動走行できる方法を確立することを目指す。市販のCPUボード(Raspberry Pi)に赤外線カメラを組み合わせ、暗視下のリアルタイム動画処理システムを構築する。 | ||
| 3 | 大島商船高等専門学校 商船学科 山口研究室 |
◎上遠野 巧、牧野 綜太 |
| 熱で海岸をきれいにするプロジェクト | ||
|
|
||
| 周辺各国から流出し、日本の海岸に漂着するゴミが問題になっている。そのほとんどはプラスチック類であり、中でも大きな発泡スチロールは目をひく存在である。当初、これを油に戻して燃料にしようと考えていたが、保管や輸送に容積の大きさが問題になっていることがわかった。効率的に減容化できる最適な温度を決定し、大型の発泡スチロール製フロートにも対応できる減容化装置を開発したい。 | ||
| 4 | 大島商船高等専門学校 自然エネルギー研究会 商船学科 川原研究室 |
◎宮田 顕宙 |
| 放射線の軌跡を捉える高感度クラウドチャンバー製作と放射線観察 | ||
|
|
||
| 放射線は目で見ることができないのでイメージしづらいという課題がある。直感的に放射線の理解を行える可視化技術に注目し、α線やβ線およびγ線といった放射線の存在を白いアルコールの霧として観察できる霧箱(クラウドチャンバー)という観察装置を用いる。熱電対や感温液晶シートで温度を計測してヒーターを精密にコントロールし、様々な温度条件での過飽和状態を作り、放射線計測に与える影響について観察する。 | ||
| 5 | 呉工業高等専門学校 機械工学科 |
◎彌吉 崚太 (呉高専 自動車部) |
| 自動車の捨て熱を刈り取る? | ||
|
|
||
| 現在の自動車エンジンにおいて、燃焼によって得られる熱エネルギーの30%程度しか、走行エネルギーとして利用されていないと言われる。また、太陽熱エネルギーもある。たとえば、自動車周辺の高温部を見つけ、熱電エネルギー変換素子であるペルチェ素子などを活用して、得られた電気エネルギーを二次バッテリーに蓄電すれば、蓄電補助機器や室内の空調補助機器など、様々な機器に有効活用することができるのではないかと考えた。 | ||
| 6 | 東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 釜道研究室 |
◎鈴木 元哉、木村 佳史郎、野口 裕司 (プロジェクト釜) |
| 釣り糸人工筋肉を用いた発電システムの構築 | ||
|
|
||
| 温度差エネルギーが注目されている。その利用として、形状記憶合金を用いた発電システムが考案されているが、高価で生産性が低いため実用化に至っていない。釣り糸人工筋肉は、市販の釣り糸から製作できる人工筋である。材料費が安価であり、生産性が非常に高いとされていて、整音性と高いパワーマス比を有していることから、実環境においても有用であるとされている。発電システムを開発し、発電効率の検証を行う。 | ||
| 7 | 東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 岩瀬・畠山研究室 |
◎笠原 史年 (B班) |
| 熱を用いて写真を現像しよう! | ||
|
|
||
| ピンホールカメラで撮影した写真を、熱を用いて印刷することで、きれいな写真を現像できる条件を探し出すことを目的とする。レンズから入ってきた光による影の明暗を用いて被写体の輪郭を形成する。この明暗を、熱を用いて輪郭を浮き上げさせることで現像できる。ホットプレートによる加熱と、熱風発生機による加熱の2種類を用意する。露光時間と現像方法(使用機器・温度)を変化させ、最適な条件を見つけ出す。 | ||
| 8 | 東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 岩瀬・畠山研究室 |
◎高際 修平 (A班) |
| 蒸気の力でチョコレートフォンデュ! | ||
|
|
||
| 水を沸騰させ、蒸気圧でチョコレートを押し上げ、チョコレートフォンデュができるか検証することを目的とする。また、液体-気体間の状態変化と水の飽和水蒸気圧について理解を深めることも目的とする。ホットプレートで水を沸騰させることで、液体から気体になることで体積が増える。この原理を利用して、ポリカーボネートの仕切り板を押し上げチョコレートを押し出し、チョコレートフォンデュを行う。 | ||
| 9 | 福井工業高等専門学校 物質工学科 |
◎日置 七瀬 (枝豆食べ隊) |
| “反応熱で枝豆を食べたい!” | ||
|
|
||
| 中和熱は、酸とアルカリを混合することで発生する。熱が容器の外に逃げないと仮定すると、水酸化ナトリウムと塩酸の反応熱に、水酸化ナトリウムの水への溶解熱を加えれば、計算上は100℃まで到達できることになり、枝豆を十分に茹でることが可能であると考えた。また、枝豆には鞘がついており、水酸化ナトリウムが枝豆に浸透する前に中和反応を起こすことができれば、塩味のきいた美味しい枝豆が食べられると考えた。 | ||
| 10 | 山梨大学 工学部 応用化学科 (山梨大学クリスタル研究センター) |
◎近藤 浩紀、小林 洋介、橋本 拓真、波多野 有那、 志村 智一、白勢 裕登、古山 貴也、松下 大希 (ケミカル cooker) |
| 化学反応を使った携帯型調理器作ろう ~ 災害時でもおいしいごはんを ~ | ||
|
|
||
| 化学反応を利用した携帯型調理器を考案・開発することを目的とする。生石灰(酸化カルシウム)の加水による発熱反応の温度上昇、継続時間を測定し、米を炊いたり、肉を焼いたりできる条件に達するかを調べる。更に、生成される消石灰(水酸化カルシウム)を加熱し、再び生石灰にリサイクルする方法を検討する。最終的に、災害時簡単使るような携帯型調理器に仕上げていく。 | ||
| 11 | 山梨大学大学院 医工農総合教育部 工学専攻 機械工学コース 武田研究室 |
◎村田 祐一、小塚 達也、田中 裕大、土屋 公俊、 人見 一輝、村松 範彦 |
| 熱音響エンジを使って車、船を動かそう! | ||
|
|
||
| 排熱を利用する技術の一つに、熱エネルギーと音エネルギーの相互変換を利用した、熱音響技術がある。熱エネルギーから音エネルギー、さらにそれを動力に変換する装置の実証を目的とする。発生した音波の振動を、圧電素子に伝えて起電力を生じさせ、電力をモーターに伝えて動力を得る。車の場合はモーターのシャフトにギアを取り付け、船の場合は直接モーターでスクリューを駆動させる。 | ||
| 12 | 山梨大学大学院 医工農総合教育部 工学専攻 機械工学コース 武田研究室 |
◎人見 一輝、小塚 達也、田中 裕大、土屋 公俊、 村田 祐一、村松 範彦 |
| フルイダインで船を作ろう! | ||
|
|
||
| 熱源の種類を選ばず、爆発を伴わない外燃機関であるスターリングエンジンが注目されている。一般的なスターリングエンジンは、2つのピストンを有するが、ピストンの代替として、水などの液体を用いるフルイダインに着目した。ピストンが流体であるため、動力源として利用することは困難とされているが、構造が簡単なフルイダインを用いてポンプを製作して、これにより船を動かすことを目的とした。 | ||
■ 第9回コンテストから継続進行のチーム
| 21 | 山梨大学大学院 医工農学総合教育部 工学専攻 機械工学コース 山梨大学 工学部 機械工学科 鳥山研究室 |
◎小林 拓矢、NDUMA JOHN NGANGA 浅野 佳祐、鈴木 満春、日高 拓哉 |
| ロケットストーブを利用して車を走らせよう! | ||
|
|
||
| カルノーサイクルの定義から分かる通り、熱源からエネルギーを取り出す効率は、温度差が大きいほど良くなる。そこで小型化可能な高温燃焼を実現できるロケットストーブに注目する。ロケットストーブは高温熱源のみならず、排気圧も比較的強いため、様々な形でエネルギーを取り出すことが可能である。エネルギーの取り出し方法および性能を評価するとともに、それを動力源とする、人が乗ることができる4 輪車を作成することを目的とする。 | ||
