LABORATORY熱の実験室
- ホーム
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
- 第4回 実験レポート
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
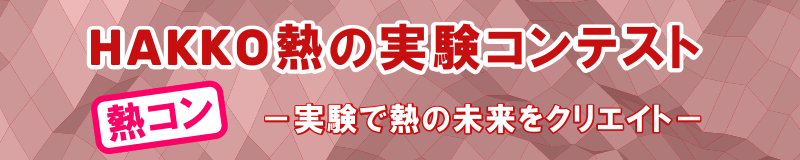
■ 「第4回 八光熱の実験コンテスト」 実験レポート
実験を実施したチームの、実験レポートです。
連番1のチームは、進行が遅れたため、次回コンテストの審査対象とします。
連番1のチームは、進行が遅れたため、次回コンテストの審査対象とします。
| 連番 | 所属 (応募時点) | 実験メンバー (チーム名) |
| 実験タイトル | ||
| 実験レポート | ||
| 所属50音順・敬称略 | ||
| 1 | 一関工業高等専門学校 機械工学科 | 伊藤 修人 (一関高専発明同好会) |
| 電磁波による野菜・食肉などへの影響 | ||
| --次回コンテストの審査対象とする-- | ||
| 野菜、食肉などに様々な電磁波を照射し、細胞変化の様子を観察し、電波の危険性について考察する。また、複数の電磁波を組み合わせ、それぞれの食材料の美味しさを引き出す加熱法について考察する。 | ||
| 2 | 茨城工業高等専門学校 専攻科 | 山越 好太 |
| 回路基板用の簡易リフロー実験 | ||
| 近年、電子回路を作製するための素子が表面実装タイプになってきており、簡単な回路を試作するためにも、表面実装部品をハンダ付けするリフロー装置が必要になってきている。遠赤外線ヒーターとシート状発熱体を利用して温度をコントロールし、また、ファンとペルチェ素子を利用した冷却により、安定なハンダ付けを行うための条件を明らかにするとともに、マイコンによる自動化を行ってみる。 | ||
| 3 | 茨城大学大学院 理工学研究科 機械工学専攻 神永・松村研究室 |
江口 悠太、堀江 亮、堀川 篤史 |
| 熱を使って演奏しよう! | ||
| 神事の一つに、「鳴釜神事」というものがある。沸騰した湯を張った釜の中ほどにセイロを乗せ、そこに冷たい玄米を振り撒く。すると、唐突に「ボーッ」という低く大きな音が一定時間鳴り響く。本実験では、釜鳴りそのものの発生メカニズムを明らかにするために、まず釜鳴りの実験装置を正確に製作し、釜鳴りの発生条件の調査、その際の各データを採取・解析を行う。そして、複数の音程(1オクターブ)を出せる装置を作製することを目的とする。可能ならば、音楽を演奏させる。 | ||
| 4 | 大阪産業大学 工学部交通機械工学科 | 外城 大将 |
| 燃焼合成反応熱を用いた新しい熱気球を大空に揚げよう | ||
| 今までの熱気球は、燃料の酸化燃焼を利用しているため、熱風を吹き込む孔が必要となり,バルーン内部の空気を暖める以外に,その一部はバルーン外に放散し熱効率が悪くならざるを得ない。一方、セラミックスなどの製造方法の1つである燃焼合成は、酸素を必要としない非酸化燃焼に属しており、元素混合粉末から化合物を生成する際に多量の化学反応熱を生ずる。この生成熱を利用して、バルーン内部の気体を暖めることで、高効率な密封系の熱気球を揚げることを主な目的とする。 | ||
| 5 | 金沢工業大学大学院 工学研究科 藤 秀実 研究室 |
飯塚 健太 |
| ジェットエンジン 燃焼器出口温度分布の均一化に関する実験 | ||
| 航空用あるいは陸舶用ガスタービンに要求される高温化、NOx低減化のためには、高温燃焼ガスと希釈空気の混合促進技術に開発が重要であるといえる。従来、混合促進は主に希釈空気孔の孔径・配置の最適化を図ることで行ってきたが、さらに混合促進を図るため、希釈空気孔出口形状自体に工夫を図る。希釈空気孔形状は円筒形に限られていたが、希釈孔の濡れ面の大きさと、混合促進の関係などについて、希釈孔形状をいろいろ変化させ混合促進に関する実験を行う。 | ||
| 6 | 信州大学 理学部化学科 | 服部 薫 (ソノファイヤー) |
| 超音波が作った水溶液中の超高温現象を調べる | ||
| 超音波を水溶液に照射するときにキャビテーション気泡と呼ばれる微小気泡ができ、これが壊れる際に熱エネルギーを放出して数千度にも達する。つまり、水溶液の中で局所的な超高温(ホットスポット)の反応場が形成できる。高温反応場(水溶液中の小さな炎)は一般的に目に見えないが、身近に理解するには、高温反応場の観測が必要であり、高速度マイクロプローブカメラによる水の中で進行する金属の熱溶接、気泡の発光現象、高温反応による有機化合物の分解などの実験を行なう。 | ||
| 7 | 東京電機大学大学院 未来科学研究科 ロボットメカトロニクス学専攻 |
伊東 譲、佐久間 智之、澤口 英太、 新原 啓央、鈴木 佑多 |
| 熱磁気エンジンカーをつくろう | ||
| 太陽光や、風力を利用したエネルギー再利用が期待されており、熱エネルギーの再利用にも期待が寄せられている。そのなかでも比較的低温でも動力を得られる熱磁気エンジン(モータ)に注目し、熱エネルギー利用について考える。実際に熱磁気エンジンを作製し、これを動力とした自動車模型を実現する。内燃機関や電気モータと比較して、簡単な構造と仕組みで動力を発生させることのできる点から、作製した模型を動かすことで、エネルギー変換技術についてわかりやすく解説していく。 | ||
| 8 | 東京電機大学 理工学部理学系 吉武研究室 |
山本 隆啓 |
| 電子レンジでinstantにインスタントコーヒーを作ろう | ||
| インスタントコーヒーを1杯だけ飲もうとするとき、ポットでお湯を沸かしたのでは時間がかかってしまうし、多量のお湯を沸かすのはもったいない。そこで、素早くて手軽な電子レンジによる加熱を思いついたが、突沸という現象が起こり、コーヒーが吹きあがることがあるようだ。電子レンジの突沸の原因を探り、これを改善し、コーヒーを素早く手軽に飲める方法を見つける必要があると考えた。 | ||
| 9 | 長野工業高等専門学校 機械工学科 | 石井 隆路 (熱の友) |
| パルス管冷凍機の試作および性能評価 | ||
| パルス管冷凍機は無潤滑で低振動であり、冷媒を用いずに一本の管で冷却することが可能である。簡単な構造の装置でも、氷点下30℃くらいは得られることがわかっているが、詳細な寸法やパラメーターは不明である。そこで、装置をまず製作し、何℃まで温度が低下するか実験条件を変えて検討する。少なくとも最低温度は0℃以下になるように、多くの条件を変え実験を行う。 | ||
| 10 | 山梨大学 工学部応用化学科 | 河野 拓人、森越 洋行、谷川 諒、 坂本 康直、丸山 恵李佳、米長 克昌 (あまごいチャレンジャー) |
| 小さな雲を作ろう!!! | ||
| 普段私たちが何気なく大空を見上げると、雲が優雅に浮かんでいる。また、山の上から見下ろすとすばらしい雲海があり感銘を受ける。そんな雲を人工的に作り出せないかと思った。雲を作る実験は、フラスコなどの容器を使って簡単にできることが知られているが、雲が容器全体に広がってしまう。本研究では、上空に浮かぶ雲のように、容器上部のみに雲を作ることを目指している。 | ||
第3回コンテストから継続進行のチーム
| 11 | 鶴岡工業高等専門学校 制御情報工学科 | 山川 敦士 |
| CPUの廃熱利用のための基礎実験 | ||
| コンピュータの廃熱を利用した発電というテーマの中でメインとなってくるゼーベック素子を生かし、温度差を変えながら発電効率を調べていくという実験をしていきたい。サーモメモリで温度を安全な状態に保ちつつ、さらに安定した発電を行えるかどうかを確かめることにした。作られた電気エネルギをどのように利用できるかも調べていきたい。 | ||
