LABORATORY熱の実験室
- ホーム
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
- 第1回 実験レポート
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
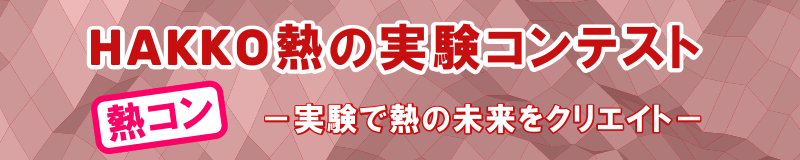
■ 「第1回 八光熱の実験コンテスト」 実験レポート
| 連番 | 所属 (応募時点) | 実験代表者 (チーム名) |
| 実験タイトル | ||
| 実験レポート(説明は実験企画時の内容) | ||
| 応募順・敬称略 | ||
| 1 | 信州大学大学院 繊維システム工学専攻 | 一色 純 |
| 地中埋設物位置の可視化 | ||
| 1. はじめに 地球上の全ての物質は温度に応じて電磁波として熱エネルギーを吸収・放射している.そこで常温付近において放射エネルギーのピークがある赤外域(8~12μm)を検出する赤外カメラで砂地表面を撮像することにより,温度に対応した輝度画像を得ることによって埋設物の位置を可視化できると考えられる. |
||
| 2 | 長野工業高等専門学校 機械工学科 | 高橋 洋平 |
| 遠赤加熱ポットを用いたゆで卵つくり器の基礎実験 | ||
| 1. 緒言 ゆで卵を作る場合には,鍋などの容器に水を入れその中に卵を入れた後,水を加熱し水が沸騰した状態で適当な時間維持する.この加熱時間の長さで,好みの硬さのゆで卵を作っている.また,水を60℃~70℃程度に保温し,その中に30 分程度卵を入れることによって家庭では温泉卵を作っている.しかし,ヒーターに卵を直接接触させ,ゆで卵を作る場合の基礎資料は明らかになっていない. そこで,本研究はノズル加熱用ヒーターを用いて,直接卵を熱しヒーター表面温度や卵の内部温度等を時系列で測定し,加熱温度や加熱時間によって卵の状態がどのように異なるかを明らかにすることを目的とする. |
||
| 3 | 信州大学工学部 機械システム工学科 | 千賀 雄介 |
| おでんに味を染み込ませる実験 | ||
| 背景と目的 おでんは煮立たせばすぐに食べられるというものではない。「ひと晩寝かせる」「何度も火にかける」というように時間と手間をかけて十分に食材の中心まで味を染み込ませることが良いとされているが、それにはゆっくりと冷却していくことがいいと言われている。また、煮込み続けなくてもよいというのは省エネにも有効であるということである。本実験ではこの「ゆっくりと冷却」を家庭にあるもので実現できる保温処理の方法を探すことを目的とする。 |
||
| 4 | 信州大学工学部 機械システム工学科 | 白川 道人 (半熟☆HERO) |
| 逆半熟たまごを作ろう | ||
| ● 実験背景 熱を利用し調理することは現在の私たちにとってごく日常的なことである.熱を使った調理法には,焼く,炒める,煮る,茹でる,揚げるなど多種多様であるが,どの調理法も外から熱を与えることにおいて共通する.加熱が十分でなかったという経験は誰しもあるのではないか. そこで,熱を内部から加えることにより食品を調理してみたいという考えに至った.熱を加えるだけで簡単においしくいただくことのできる「たまご」をとりあげ,内部から熱を加え調理する.「たまご」の選定理由には,「たまご」に含まれるタンパク質が,熱により固化する性質に注目して熱の伝わりを観察する意図がある. |
||
| 5 | 茨城工業高等専門学校 電気工学科 | 佐瀬 徹矢 |
| 光ディスクを加熱するとどうなるか | ||
| 1. はじめに 近年、地上波デジタル放送の放送開始などをきっかけとし、家庭用録画機ではVHSなどの磁気テープ媒体に替わりDVD が普及するとともにBlu-ray、HD-DVD が出現し、記憶媒体の進化は目まぐるしい発展を遂げている。それは記憶媒体の用途も広がり、当然のこととして、様々な環境で使用されることになる。 光ディスクの保存環境は、-20 度から50 度までの範囲で、使用環境は-25 度から70 度までの範囲での利用が標準的となっている。これまで、CD の規格に定められている環境条件を証明するための実験はあるが、それ以上の温度での影響は明らかになっていない。 そこで、CD の規格で決められている保存環境、使用環境を超える温度の条件で、特に80 度を超える温度では、光ディスク媒体であるCD-R 及びCD-RW 媒体のデータにどのような影響が生じるのかを実験的に検討した。 |
||
| 6 | 長野工業高等専門学校 機械工学科 | 中村 圭貴 |
| 水加熱用ヒーターまわりの流れの可視化 | ||
| 1. はじめに 水や油の加熱用ヒーターには多くの種類がある.その断面形状は一般的に円形であるが,ヒーターの全体形状はさまざまである(1). ところで,円柱まわりの自然対流の流れの可視化に関する研究(2)は報告されているが,市販されているヒーターを加熱した場合のそのまわりの流れを観察した報告例は少ない. そこで,本研究は市販の5 種類のヒーターを加熱し,そのまわりの流れの可視化をコンデンスミルク法とPIV 解析によって試みた. |
||
| 7 | 東京都立科学技術高等学校 科学研究部 | 相川 幸平 |
| 植物からガラスを作る | ||
| はじめに 科学研究部の先輩たちは、これまで「植物を利用した環境浄化」の研究に取組んできました。私たちのグループは、そこから学び植物が吸収する二酸化ケイ素SiO2に焦点をあてて、その元素を取り出すことでガラスをつくるという研究に取組みました。 また、都立科学技術高校のある江東区は、伝統工芸技術である「江戸切子」の継承地域です。科学と工業技術を学ぶ私たちは、地元の伝統の技・匠「江戸切子」を学びながら、授業で取り上げられている「ものづくりの大切さ」について考えました。 |
||
| 8 | 信州大学繊維学部 機能機械学科 | 岸元 修平 (2007/3 まで) |
| 信州大学 総合工学系大学院 | 島川 聡 (2007/4 から) | |
| アウトドアで使える熱電発電による携帯電話充電器 | ||
| 充電に成功した【追加報告】: |
||
| 1. 目的 キャンプ、登山時などのアウトドアで電池切れをして大変困ることがある。そんな際、手軽に携帯電話を充電することができる熱電発電器の開発と試作を研究目的とした。 発電の原理は良く使われる熱電対と同じゼーベック効果を利用したもので、異なる材料の2 本の金属線を接続して1つの回路(熱電対)をつくり、ふたつの接点に温度差を与えると、回路に電圧が発生するというものである。一般的に、熱電対を直列に多数繋ぐことによって熱電堆とすれば、感度の良い温度センサとなることは知られている。この熱電堆を使用することによって、熱源があればどこでも十分な発電することが可能である。 中間報告では340mV しか発電できなかったが、本報では改良を加え起電力を高めた新型の熱電発電による携帯電話充電器について報告する。 |
||
| 9 | 長野工業高等専門学校 電気電子工学科 | 佐藤 知宏 |
| ポンポン船を電気ヒーターで走らそう | ||
|
1. 目的 環境負荷や有限であるという点から,化石燃料等の天然資源を永年に渡って使用していくのは年々難しくなっている.電気の世の中になったとはいえ暖房などの熱源は世界的にも電気の割合少なく,火を使っている.しかし電気ほど容易,安全,エコなエネルギーは他にはない.そこで電気と燃料による熱源の代替を行った際の問題点を検証する. |
||
| 10 | 信州大学工学部 機械システム工学科 | 竹内 克也 (熱ちゅー部) |
| 0℃でも凍らない水 | ||
| 実験目的 水が0℃になると氷に変化することは誰でも知っている事実です。しかし様々な条件により0℃以下に冷やされても水が凍らず、液体の状態のままである場合があります。 植物は地中から水分を吸収しており、当然植物内にも水分が存在します。しかし冬場、氷点下を迎えた朝でも植物がカチカチに凍結していることはほとんどありません。それは植物の中を流れる水の通る管が、とても細いためであると言われています。細い管の中の水は,管の表面と水素結合で結びつき,束縛された液体となるため,氷に相変化しにくいと言われています.つまり細い管の中の水は、0℃以下に冷やしても凍らないということになります。そこで一般に手に入るチューブを用いて、その中の水が本当に0℃でも凍らないのか,実験してみました。 |
||
