LABORATORY熱の実験室
- ホーム
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
- 第2回 実験レポート
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
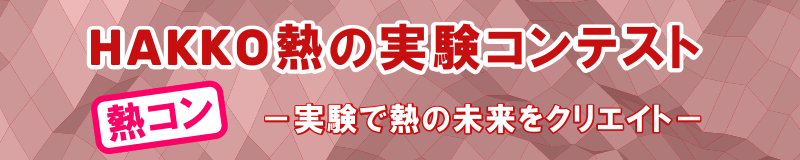
■ 「第2回 HAKKO熱の実験コンテスト」 実験レポート
| 連番 | 所属 | 実験メンバー (チーム名) ◎は代表者 |
| 実験タイトル | ||
| 実験レポート(説明は実験企画時の内容) | ||
| 所属50音順・敬称略 / 記載内容は、応募時点のものです。 | ||
| 1 | 秋田大学 理工学部 創造生産工学コース 足立研究室 |
◎高橋 祐篤、佐藤 靖憲、櫻庭 由紀乃、高橋 賢司 (足立研究室チーム) |
| アルミ網とIoT を用いて道路融雪を効率的にやろう! | ||
|
|
||
| 寒冷地の積雪や凍結を解消するためのロードヒーティングは、多くの電力を消費しており、このコストを削減することは雪国の重要な課題。道路表面の熱分布を均一化する方法として、電熱線方式のロードヒーティングに、アルミ金属網を組み合わせたヒーターの有効性を検証する。制御方法として、スマートフォンなどのカメラをインターネットに接続し、降雪の状態を画像認識で判断するシステムを検討する。 | ||
| 2 | 大島商船高等専門学校 商船学科 山口・浦田研究室 |
◎上遠野 巧、斎藤 香澄、牧野 綜太 |
| 熱を使ってリサイクルについて考えてみよう | ||
|
|
||
| 海岸清掃活動で、発泡スチロール以外のプラスチックについても、減容化や処理について求められた。誰にでもわかりやすいプラスチック類の分別と再資源化について、実験を用いながら広めていきたい。また、プラスチック類の再資源化として、卓上型の小型プラスチック油化装置の開発を行う。熱可塑性のプラスチックの温度と変形について検証することにより、各種プラスチック類の減容化についても考察する。 | ||
| 3 | 神奈川大学 工学部 機械工学科 原村研究室 |
◎加藤 巧海、田首 孝次朗 |
| 球形ヒートパイプによるLED 冷却 ~LED 電球冷却面積の飛躍的拡大~ | ||
|
|
||
| LEDの発熱を電球表面全体に伝えて、放熱を増進する電球の実現性について実験的に調べる。冷却性能を向上させて、より明るく、より小さいLED電球の実現をねらうとともに、対流を抑制する設置状況でも、放射による冷却が確保されるような放熱モードの実現をねらう。ヒートパイプの原理を用いて、3Dプリンターで製作した樹脂製の溝形ウィックを球殻に取付ける案、ガラスビーズを球内面に並べる案について、試作する。 | ||
| 4 | 岐阜県立岐阜農林高等学校 食品科学科 食品化学分析班 |
◎納村 文博、加藤 晴代、金田 凛太、横田 なつみ、吉田 真夕 |
| 醤油粕を使い捨てカイロへ利用するための発熱試験 | ||
|
|
||
| 醤油の製造工程で、もろみを圧搾機で搾る際に、「醤油粕」が生じる。これは原材料の大豆および割砕煎り小麦由来の固形物で、産業廃棄物として廃棄している。この醤油粕を、安価で簡易な方法で再利用するための技術を開発することを目的とする。醤油粕に含まれている多量の食塩を活かして「使い捨てカイロ」の、鉄粉と食塩を混合させることで酸化反応が促進され高温が瞬時に発生する、発熱媒体として利用できないか検討する。 | ||
| 5 | 高知工業高等専門学校 電気情報工学科 高田研究室 |
◎上園 波輝、秋元 優貴、岡村 友樹、加藤 樹、楠目 啄也 |
| Raspberry Pi 周辺の熱移動の見える化実験 | ||
|
|
||
| Raspberry Pi を、熱環境の厳しい状況で観測装置に使用するとき、熱移動を把握し、装置全体の熱管理を行うことが重要となる。等間隔に配置した温度センサを用いて、装置内の3 次元の温度分布の時間変化を把握する。さらに、サーモグラフィーカメラを利用し、Raspberry Pi 基板付近での温度分布の時間変化を視覚化する。10hPa程度の低圧、-20℃程度の低温での実験も行い、様々な環境下での温度分布の時間変化から、温度変化の定式化について考察する。 | ||
| 6 | 神戸市立工業高等専門学校 機械工学科 |
◎永井 明里 |
| 金属間化合物の反応熱でバターを溶かす!? | ||
|
|
||
| アルミニウム(Al)とニッケル(Ni)原子が隣接混合した状態に、電気スパークなどの微小エネルギーを与えると、Al-Ni系金属間化合物を形成すると同時に大きな発熱を生じる。この反応熱で食用バターを溶かす実験を行い、理想的にバターが溶ける温度、Al/Ni発熱材料とバターの質量比の最適値を求め、冷蔵庫から取り出したバターをすぐにトーストに塗ることができる、加熱式バターナイフ「MeltyDipper」を開発する。 | ||
| 7 | 東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 畠山・岩瀬研究室 |
◎金子 仁、佐藤 泰彦、小谷 宙、川越 健太、金田 啓太郎 山門 拓己、ソウ キン、中川 雄大、中村 正太朗、藤原 翔 村上 賢太郎 (A班) |
| お風呂の温度を浴室外で体感しよう | ||
|
|
||
| Raspberry Pi Zero W,温度センサおよびペルチェ素子などディジタル回路を用いて、熱を入力として浴室外の別室で水温情報を体感する。浴槽内に入れた温度センサから得られた水温情報を、Raspberry Pi Zero Wで、無線LANを通して送信する。別室に設置したRaspberry Pi Zero Wで受信し、ペルチェ素子を用いて受信した水温情報を体感できるようにする。 | ||
| 8 | 東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 畠山・岩瀬研究室 |
◎熊木 陽洋 (B班) |
| 熱収縮アクチュエータを用いた5指式マニピュレータの製作 | ||
|
|
||
| 5指式マニピュレータのアクチュエータとして使用することで、釣り糸人工筋肉と形状記憶合金の性能比較をする。釣り糸人工筋肉は、電流を流すことで発熱させると縮む性質があり、指を稼働させることができる.形状記憶合金は、加熱時に記憶した形状に戻る性質があり、バネ状の形を記憶させた形状記憶合金を指に配置することにより、ニクロム線で加熱することで指を稼働させることができる。 | ||
| 9 | 沼津工業高等専門学校 機械工学科 マイクロデバイス研究室 |
◎米澤 諒太 |
| 熱拡散現象を応用したマイクロ流体デバイスによる混合溶液の分離 | ||
|
|
||
| 温度勾配を付与するこで、濃度勾配が形成される現象である、熱拡散現象を用いたマイクロ流体デバス使って、水素同位体であるトリチウム水と軽水を分離させる。マイクロ流体デバイスシステムは、上から高温、下から低温かけ熱拡散現象を発生させ、流出口に上下に分かれるセパレータを設けることで溶液を分離させる。 | ||
| 10 | 山梨大学 工学部 応用化学科 クリスタルゼミ |
◎八板 光輝、芝田 昌典、清水 陽向、宮沢 健史、柴崎 有紀 矢ヶ崎 恵斗、吉村 元希、市野 祥多 |
| 磁石でコーラを冷やそう ~室温磁気冷却システムの開発~ | ||
|
|
||
| 磁性体を励磁した時の発熱を系(冷却システムの外)の外に排出し、減磁した時の吸熱を利用して系を冷却する、磁気冷却技術を用いて、飲み物を冷やす冷却システムを製作する。磁石の移動や回転によって、減磁と励磁を繰り返し行うことで冷却材料(磁性体)の磁性の向きを変化させて、系の温度を徐々に下げていく。 | ||
