LABORATORY熱の実験室
- ホーム
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
- 第1回 実験レポート
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
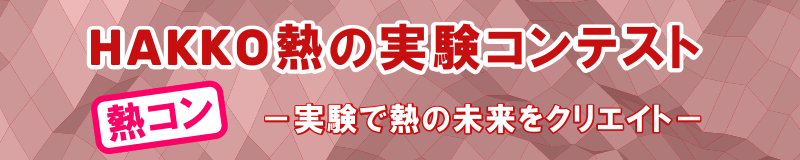
■ 「第1回 HAKKO熱の実験コンテスト」 実験レポート
| 連番 | 所属 | 実験メンバー (チーム名) ◎は代表者 |
| 実験タイトル | ||
| 実験レポート(説明は実験企画時の内容) | ||
| 所属50音順・敬称略 / 記載内容は、応募時点のものです。 | ||
| 1 | 大島商船高等専門学校 商船学科 内燃機関実験室 |
◎古川 幸之介 |
| 身近な材料を用いた圧気発火器の製作と瞬時現象実験 | ||
|
|
||
| ガソリン機関では、混合気を点火装置により爆発・燃焼させるので、その仕組みは理解しやすいが、ディーゼル機関などの、空気を圧縮すると温度が上がるという仕組みを、感覚的・体験的に理解させることは比較的困難である。身近な材料を用いて圧気発火器を製作し、圧気発火器内部の可視化と瞬間的な物理現象の計測できるように装置の改良を行い、実際の現象をどの程度捉えることが可能であるか検討する。 | ||
| 2 | 金沢工業高等専門学校 電気電子工学科 |
◎永山 尚也 (永岩寺東沢(えいがんじとうたく)) |
| 電気炉で電池用炭を製作する実験 | ||
|
|
||
| 電気炉を用いて、木材を炭化して炭を製作するための焼成パターンを見つけ出す。電気炉では、高い温度で焼成すると木材が燃えてしまうだけで炭にはならない。そこで、水分の蒸発、表面の焼成、芯部分の炭化をさせる必要がある。この過程で、電気炉内の燃焼を温度変化で制御することが必要である。その温度パターンを実験により見つけ出し、できた炭は照明用炭電池として、点灯寿命実験で比較する。 | ||
| 3 | 高知工業高等専門学校 電気情報工学科 |
◎坪内 麟太郎、上園 波輝、川上 舞帆、笹岡 由唯 |
| Raspberry Pi の発熱効果と保温性能の評価実験 | ||
|
|
||
| Raspberry Pi を用いた気球搭載観測装置を開発しており、上空20 km 以上の成層圏に至る経路の気象観測を目指しているが、低温の状態が長時間続くような場合には、装置を保温する必要がある。オンボードコンピュータの発熱を保温に利用することで、装置内の温度が下がりすぎることを防ぐことができるかもしれない。保温として使うことを目指し、Raspberry Pi の発熱と保温性能の評価実験を行う。 | ||
| 4 | 東京電機大学大学院 未来科学研究未来科 ロボット・メカトロニクス学専攻 |
◎森田 和希、村木 一平、鈴木 元哉、木村 佳史郎、野口 裕司 (プロジェクトバイオ釜 2nd) |
| 熱で動くミミズ型ロボットを作ろう! | ||
|
|
||
| 災害現場での活躍が期待されている小型ロボットの一例として、ミミズの移動メカニズムを模倣して前進する、ミミズ型ロボットがある。市販の釣り糸をひねってコイル状に成形することで製作することができる、柔らかく高出力な釣り糸人工筋を用いた、世界最軽量・最安価な熱で動くミミズ型ロボットの開発を行う。実際のミミズと競争・比較させることで、ミミズ型ロボットの性能を評価する。 | ||
| 5 | 東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 畠山・岩瀬研究室 |
◎岡部 稜河 (A班) |
| 油なしで揚げ物を作ろう! | ||
|
|
||
| 食品に熱風を吹き付けることで表面の水分を蒸発させ、油を使わずに揚げ調理を行うこと、また、そのために適切な温度や加熱時間を検証することを目的とする。実験装置に熱風発生機を接続し、高温の気体で継続して加熱することで、 食品を内部まで十分に加熱する。 | ||
| 6 | 長野工業高等専門学校 機械工学科 |
◎佐塚 光平 |
| 感温液晶シートを用いた半円筒内面の衝突噴流熱伝達率の測定 | ||
|
|
||
| 凹面への衝突噴流は、ガスタービン静翼内部の冷却や曲げ加工面の冷却など、工業上多くの利用例がある。しかし、平坦な面の衝突噴流熱伝達に関する研究に比べると、凹面の衝突噴流熱伝達の研究は少ない。実験装置から空気噴流を水平に噴出させ、それを噴出口と等間隔に離した凹面に衝突させる。その面の衝突噴流熱伝達率分布を感温液晶シートの色分布から明らかにし、伝熱促進の条件を明らかにすることを目的とする。 | ||
| 7 | 名古屋大学工学部機械・航空工学科 長野研究室 |
◎西保 裕司、高島 晃、宮地 耕平、横山 翔平 |
| 毛管現象を使って発電し、その電気で物を浮遊させよう!! | ||
|
|
||
| 毛細管力とは、メニスカスが形成される界面において、表面張力によって働く力である。その力を利用して受熱部で受け取った熱を、電力を使わずに放熱部まで受動的に輸送する熱機関のことを “ループヒートパイプ”(LHP)と呼ぶ。LHP の過程の途中にタービンなどを設置することで、モーターを回し発電するという、新しい原理を考えた。太陽熱によってこれを稼働させ、生じた電気によりモーターを回し、ホバーカーを浮かせ、走らせる。 | ||
| 8 | 山梨大学大学院 医工農学総合教育部 工学専攻機械工学コース 武田研究室 |
◎渡邉 征弥、藤上 健太、丸茂 勇貴、志賀 倫哉 |
| 潜水・浮上!そして動く!潜水艇 | ||
|
|
||
| 潜水艇の潜水・浮上の原理はよく知られているが、実際にそれを体感できる機会は少ない。そこで、潜水・浮上の原理に、熱による温度上昇に伴う空気の膨張を利用した潜水艇を考案した。発熱材を使い空気を膨張させ、潜水艇の浮力を大きくすると同時に、90℃の熱湯を用い、周囲の水との温度差から熱電変換素子により電力を発生させ、潜水艇の動力に利用するシステムを構築する。 | ||
| 9 | 山梨大学大学院 医工農学総合教育学部 工学専攻機械工学コース 武田研究室 |
◎丸茂 勇貴、藤上 健太、渡邉 征弥、志賀 倫哉 |
| 地中熱ヒートポンプで温水をつくろう! | ||
|
|
||
| 地中熱を利用した省エネルギーシステムは、日本での知名度が低く、初期投資コストが高いことなどの理由で補助金に頼っているのが現状である。従来システムの冷媒/不凍液熱交換器を取り除き、冷媒の熱を直接地中と熱交換する。また、垂直埋設型のボアホール利用をやめて、地中熱交換器を水平に設置して掘削コストを削減する。出力の小さい給湯システムを、小型の地中熱ヒートポンプにより製作することを目標とする。 | ||
| 10 | 山梨大学 工学部 応用化学科 (山梨大学クリスタル科学研究センター) |
◎白勢 裕登、志村 智一、古山 貴也、松下 大希、 柴田 昌典、清水 陽向、宮沢 健史、八板 光輝 (Electric Baker) |
| 隠し味『電解質』~美味しい電気パンを作ろう~ | ||
|
|
||
| パン生地がホットケーキミックスの場合、この中に含まれる電解質(水に溶かすとイオンに分解される物質)である、重曹と呼ばれる炭酸水素ナトリウムに電気が流れた際に熱が発生し、この熱で炭酸水素ナトリウムが分解され、発生する二酸化炭素が気泡となってパンを膨らませる。電気パンのメカニズムを知るとともに、パン生地に入れる電解質の種類や量を変え、発酵したパンに劣らないおいしいパンを作ることを最終目標とする。 | ||
