LABORATORY熱の実験室
- ホーム
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
- 第9回 実験レポート
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
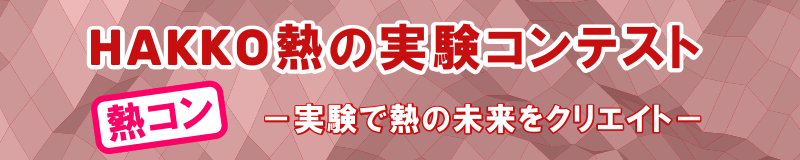
■ 「第9回 八光熱の実験コンテスト」 実験レポート
| 連番 | 所属 (応募時点) | 実験メンバー (チーム名) ◎は代表者 |
| 実験タイトル | ||
| 実験レポート(説明は実験企画時の内容) | ||
| 所属50音順・敬称略 | ||
| 1 | 茨城工業高等専門学校 電気電子システム工学科 |
◎石井 晴乃、我妻 瞳、植前 美紀、加藤 美夕、熊谷 ひかる、 西丸 真生、佐藤 汐莉、関根 喜涼、高野 さつき、根本 瑞希、 山口 英莉、横須 賀歩 (高専E☆girls) |
| 空飛ぶ目玉焼き ~自己発電で空を飛ぶ、目玉焼き気球の製作~ | ||
|
|
||
| 太陽光発電モジュールを気球の球皮の一部とすることで、自己発電しながら飛行可能な気球を製作できるのではないかと考えた。発電した電気を熱に変換し、球皮内の空気を暖めて上昇気流を発生させる、熱気球と同様の機構を検討している。この際、ただ単に電気を熱にして気球を飛ばすだけでは面白くないので、同時に目玉焼きも焼きたいと考えた。 | ||
| 2 | 茨城大学 工学部 機械工学科 茨城大学大学院 理工学研究科 機械工学専攻 松村研究室 |
植田 亮、玉根 正貴 ◎関 真之 |
| ジェット気流を可視化して地球の異常気象について調べよう!! | ||
| 伝熱工学・流体力学の視点から、ジェット気流の形成過程とその流れのパターンを可視化する装置を製作し、地球規模のジェット気流を解明することを目指す。まず物理現象を実際に直接目で見て確認し、それを直感的に理解し体感することのできる、理科学教材としても役立つ実験装置の製を目的とする。また、作成した装置を利用して実験条件を変えながら、ジェット気流の蛇行や地球の異常気象の関連性について調べることを予定している。 | ||
| 3 | 岩手大学 工学部 機械システム工学科 廣瀬・福江研究室 |
◎嵯峨 遥介 (Heat Think Lab.) |
| 蒸気機関を用いた二足歩行ロボットの作成 | ||
| 蒸気機関を使った二足歩行ロボットによって、子供たちに熱や機械への興味をもってもらうことを想起した。チェビシェフの原理(サイクロイド曲線を利用した、二足歩行の機構)を利用することで、早戻り機構、擬似直線運動機構を実現することができる。蒸気機関で動く二足歩行ロボットを、500ml ペットボトル一本分の水で1m 動かすことを目標にする。 | ||
| 4 | 呉工業高等専門学校 専攻科 機械電気工学専攻 機械系 |
◎古久保 佳男 |
| 熱で泳ぐ魚ロボット? | ||
| 魚類を模した尾ひれ推進機構は、生態・環境への影響が少なく、エネルギー的にも効率が良いと言われているが、工業面への実用化までには至っていない。そこで、小型の尾ひれ推進装置の実用化を目指しつつ、ホビースケールで製作・改造のしやすい「熱エネルギーで泳ぐ魚ロボット教材」の開発を行う。乾電池と同等の動力を得ることは難しいので、回転運動→往復運動を利用する。 | ||
| 5 | 神戸市立工業高等専門学校 機械工学科 |
◎廣澤 謙弥、長澤 直樹、親川 暢、梅井 純平、藤田 克伸 (神戸高専熱研動力研究チーム) |
| 炎のプレートでおいしくクッキング! | ||
| プレート状に平面的な火炎面を形成できる、平面火炎バーナーを利用し、加熱炉を製作する。その加熱炉の温度特性を測定し、またさまざまな物体を加熱して、通常の拡散火炎で加熱した場合との違いを調査する。この炉を用いて、実際に物体の加熱を行う。例えば、粘土から陶器を焼成して、どのように焼きあがるのか、あるいは食品を加熱してみて、通常のバーベキューコンロで焼いた場合と味は違うのか体験する。 | ||
| 6 | 筑波大学大学院 生命環境科学研究科 負荷適応分子生物学研究室 |
◎返町 洋祐 |
| 熱によるゴムの収縮を利用したアクチュエータの製作 | ||
| 一般的な物質では、原子・分子の熱による振動が激しくなると体積が増加するのに対し、ゴムの場合には、振動によって分子鎖が一層乱雑に絡み合うために体積が低下する。ゴム紐の熱による収縮を動力としたアクチュエータの製作を試みる。腕が筋繊維の収縮と弛緩によって動くように、ゴム紐を熱で操り、ロボットアームを動作させる。最終的には、ピンポン玉を摘み上げたり、鍋の蓋を開けたりといった動きができるような装置を目指す。 | ||
| 7 | 東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 岩瀬・畠山研究室 |
◎山崎 正博 |
| 電熱製品で綿菓子を作ろう! | ||
| 熱風発生機で熱風を発生させ、プロペラを取り付けたアルミ缶を回転させることで綿菓子を作ることができるか検証する。アルミ缶に取り付けるプロペラは、正面から風を受けることで揚力が発生し、この揚力によって回転する、揚力形プロペラ風車を参考に製作する。熱風をプロペラに当てることでアルミ缶を回転させ、アルミ缶の下方の側面に空けた穴から溶かしたザラメを放出することで綿菓子を作る。 | ||
| 8 | 松本大学 人間健康学部 健康栄養学科 矢内研究室 |
◎小沼 有里、久野 智子 |
| さつまいもの前処理が焼き芋の甘味度に及ぼす影響 | ||
| さつまいもは、単糖類や二糖類などの甘味を呈する糖を多く含むため甘さを感じる。また、主成分であるでんぷんは、それを分解する酵素であるアミラーゼによって分解され、甘味度を増す。さつまいもの加熱調理前に酵素反応によるでんぷんの分解を促進させる条件を見出せば、甘味度の高いさつまいも加工品(焼き芋など)ができると考えられる。さつまいもの加熱調理前に行う前処理がさつまいもの甘味度に及ぼす影響について、実験を行う。 | ||
| 9 | 山梨大学大学院 医学工学総合教育部 機械システム工学専攻 山梨大学 工学部 機械工学科 鳥山研究室 |
◎池田 浩輔 鈴木啓悟(特攻野郎T チーム) |
| ロケットストーブを利用して車を走らせよう! | ||
| カルノーサイクルの定義から分かる通り、熱源からエネルギーを取り出す効率は、温度差が大きいほど良くなる。そこで小型化可能な高温燃焼を実現できるロケットストーブに注目する。ロケットストーブは高温熱源のみならず、排気圧も比較的強いため、様々な形でエネルギーを取り出すことが可能である。エネルギーの取り出し方法および性能を評価するとともに、それを動力源とする、人が乗ることができる4 輪車を作成することを目的とする。 | ||
| 10 | 山梨大学大学院 医学工学総合教育部 機械システム工学専攻 武田研究室 |
◎遠藤 卓也、天野 慎也、浅利 悠太、繁松 拓未、青山 敬紀 |
| 小さな熱源も見逃さない!水に浮かべるだけの船 | ||
| 川や池などの水温と外気温との温度差が生み出すエネルギーに着目した。バネ形状を記憶した形状記憶合金を作動させ、それを動力とした船を製作し、実際に駆動させる。水温と外気温をパラメータとした際の、形状記憶合金の作動特性のデータを取得することが重要である。外気温と水温との温度差のみで駆動させるシステムの構築が目標だが、太陽光集光システムの搭載により、外気温が低い冬季でも駆動できるようなシステムを構築する予定。 | ||
