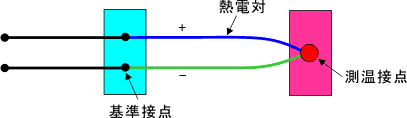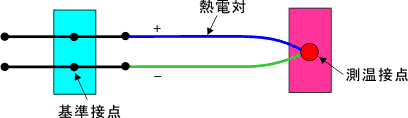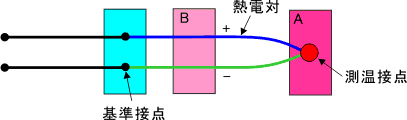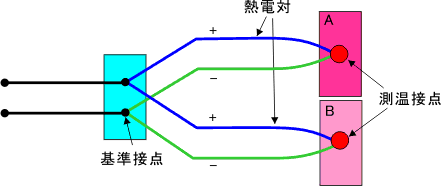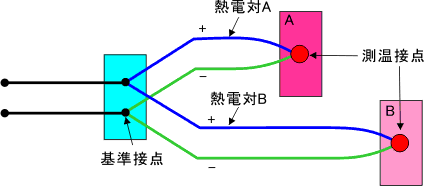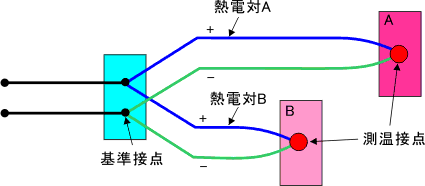● 接続-1
普通の接続です。
| ヒーター温度 |
気温 |
熱起電力 |
熱起電力から換算した温度 |
| 287.5℃ |
26.0℃ |
11.935mV |
293℃ |
ヒーター温度より、約5℃高い温度に相当する熱起電力になっていますが、ヒーターの温度はシリコーンラバーヒーター裏面に、起電力は表面に熱電対を取り付けているための、温度差のためと思われます。
● 接続-2
一般に、熱電対と計測器の間は、補償導線(熱電対とほぼ同等の熱起電力特性を有する導線)で接続しますが、補償導線使わずに普通の導線で接続すると、このようになります。
| ヒーター温度 |
気温 |
熱起電力 |
熱起電力から換算した温度 |
| 285.2℃ |
26.2℃ |
10.780mV |
265℃ |
ヒーター温度より低い温度に相当する熱起電力になっています。普通の導線で接続すると、実質的な基準接点は、その接続部分になってしまいますので、測温接点温度から気温を引いた温度に相当する、熱起電力になります。
● 接続-3
熱電対の途中の温度を、低い温度の方のシリコーンラバーヒーターBで加熱します。
| ヒーターA温度 |
ヒーターB温度 |
気温 |
熱起電力 |
熱起電力から換算した温度 |
| 280.9℃ |
181.1℃ |
25.2℃ |
11.516mV |
283℃ |
熱起電力に、熱電対の途中の温度は影響しなくて、測温接点と基準接点の温度だけで決まります。
● 接続-4
ヒーターA、Bに取り付けた熱電対を、並列に接続します。2対の熱電対の抵抗値はほぼ同じです。
| ヒーターA温度 |
ヒーターB温度 |
気温 |
熱起電力 |
熱起電力から換算した温度 |
| 285.1℃ |
178.4℃ |
26.0℃ |
9.298mV |
229℃ |
2つの測温接点の平均温度に相当する熱起電力になっています。
● 接続-5
接続-4の、熱電対Aの抵抗値(長さ)を、熱電対Bの半分にしたものです。
ヒーターA
温度 |
ヒーターB
温度 |
熱電対A
抵抗値 |
熱電対B
抵抗値 |
気温 |
熱起電力 |
熱起電力から換算した温度 |
| 270.1℃ |
177.6℃ |
24Ω |
48Ω |
26.3℃ |
9.707mV |
239℃ |
2つの測温接点の平均より、15℃ほど高い温度に相当する熱起電力になっています。
● 接続-6
接続-5の反対です。
ヒーターA
温度 |
ヒーターB
温度 |
熱電対A
抵抗値 |
熱電対B
抵抗値 |
気温 |
熱起電力 |
熱起電力から換算した温度 |
| 276.2℃ |
177.9℃ |
48Ω |
24Ω |
25.9℃ |
8.672mV |
213℃ |
2つの測温接点の平均より、14℃ほど低い温度に相当する熱起電力になっています。接続-5の結果と合わせると、並列に接続する熱電対の抵抗値が違うと、抵抗値が小さい側の熱電対の影響が大きくなっていますが、抵抗値の比率分の影響度があるわけではないようです。
|