LABORATORY熱の実験室
- 熱の実験室
- 元祖 熱の実験室
|
● 実験結果について 遠赤外線ヒーターと太陽光線で加熱したときの温度が、高い順に並べると次のようになります。
1、2、7番は同じですが、3~6 番が違っています。特に違いが目立つのが、No.6の土入りファンデーションです。No.3 のUVカットファンデーションが、太陽光線で温度が上がらないのは、その効能からしてもっともと解釈できますが、実際にはUVカットではないファンデーションが、太陽光線を良く吸収しているということのようです。大地と同じ土だからなのか、他のファンデーションも同じなのかは、わかりませんが。 ● 遠赤外線ヒーターと太陽光線の違い 遠赤外線ヒーターも、太陽も、高温のところから電磁波がエネルギーとして放射していることには変わりありません。ただ、温度が大きく違います。単位面積から放射されるエナルギー量は、絶対温度(K:ケルビン)の4乗に比例しますので、5780Kの太陽は、873Kの遠赤外線ヒーターの1922倍にもなります。また、温度の違いによって、電磁波の波長が異なることになります。
電磁波のピーク波長:λは、温度が高いほど短くなり、Wien(ウィーン)の変位則という、次の式に従います。 黒体(表面に到達する放射エネルギーを全て吸収する物体)の、波長によるエネルギー:Eλは、Planck(プランク)の法則に従います。 この法則による計算値から、ピーク波長のときを 100%としたのが、下のグラフです。 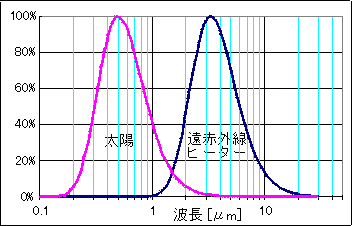 実際には、遠赤外線ヒーターは黒体ではありませんし、太陽も、多少異なった波長エネルギーになっています。補正した遠赤外線ヒーターと、地球大気外の太陽のエネルギーは、下のグラフのようになります。 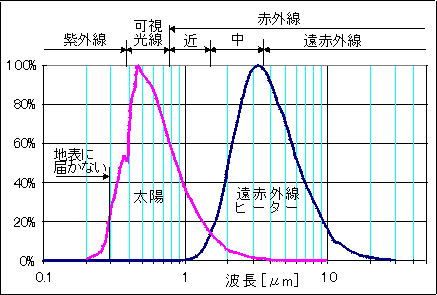 更に、太陽光線はオゾン層や大気に吸収され、地域や季節、天候、時刻などで違ってきます。0.29μ mより短い波長は地表には届かず、概ね、次の割合になっています。
人体も含めて、プラスチックや塗料、食品などは、赤外線を良く吸収しますが、物体の種類によって、波長による吸収されやすさに違いがあります。肉眼で、明るく見える色の物体は、可視光線を吸収しにくい(反射しやすい)ということで、太陽光線のエネルギーは吸収しにくい傾向があります。しかし、目に見えない赤外線の領域では、目で見た明るさと吸収しやすさには、大分違いが生じることになります。そのため、中・遠赤外線を多く放射する遠赤外線ヒーターと、短い波長の割合が大きい太陽では、加熱されやすさに違いが生じることになります。 |
