| 測定した温度と消費電力から熱伝導率を計算すると、表2のような結果になった。 |
表2 計測結果
| 断熱材 |
安定後の断熱材低温側温度[℃] |
熱伝導率 [W/(m・K)] |
| 200℃温調 |
300℃温調 |
200℃温調 |
300℃温調 |
| カタログ値 |
計測値 |
カタログ値 |
計測値 |
| セラミック系(1) |
63.5 |
93.1 |
0.07 |
0.046 |
0.08 |
0.11 |
| セラミック系(2) |
60.6 |
89.1 |
0.07 |
0.041 |
0.08 |
0.093 |
| セラミック系(3) |
58.9 |
87.8 |
0.05 |
0.047 |
0.07 |
0.116 |
| セラミック系(4) |
60.7 |
85.8 |
0.05 |
0.051 |
0.065 |
0.115 |
| 鉱物系 |
58.9 |
85.2 |
0.05 |
0.044 |
0.08 |
0.098 |
| ガラスファイバー系 |
64.1 |
91.3 |
0.067 |
0.04 |
0.09 |
0.108 |
|
試験時の計測した温度記録の一部を掲げる。
(ホットプレートの温度が同じなら、全て同じような形状のグラフになるので、代表例を掲げる。) |
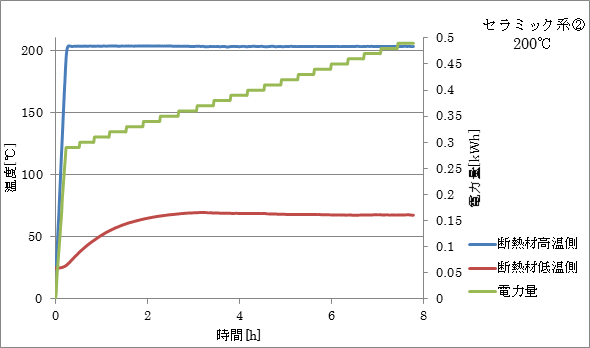
図6 セラミック系(2) 200℃温調
|
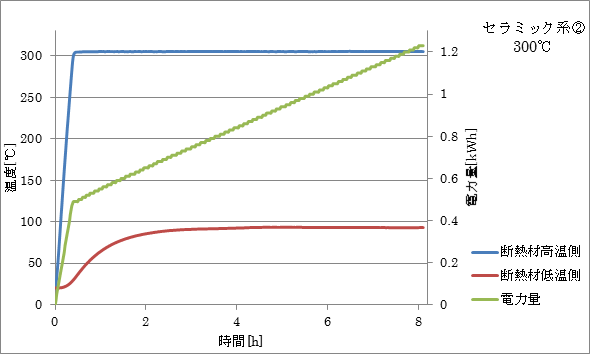
図7 セラミック系(2) 300℃温調
|
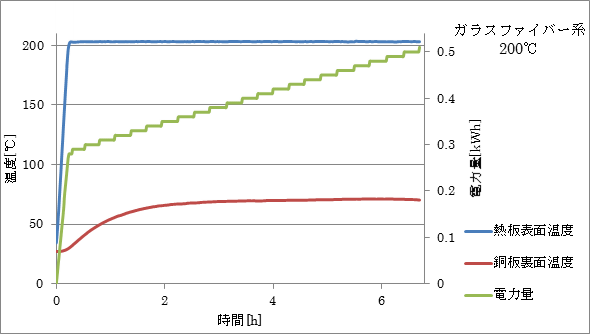
図8 ガラスファイバー系 200℃温調
|
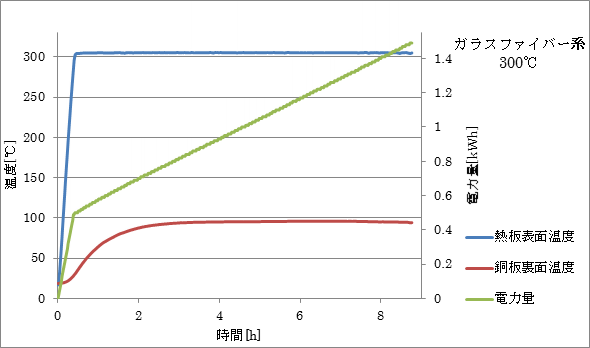
図9 ガラスファイバー系 300℃温調
|
結果より、カタログ値と比較すると200℃温調ではカタログ値より低く、300℃温調では高い値となった。考えられる要因として以下の点が挙げられる。
- 銅板やホットプレートDEMOの放熱があるため、消費電力計の測定値が断熱材に加わった正確な熱量でない
- 銅板で断熱材を挟み込んでいるため、銅板の自重により断熱材の密度、厚みが変化している可能性がある
- 熱電対の取付け方による測定誤差
- ホットプレートDEMOの温調器やデータロガー、消費電力計の精度
- 周囲環境による放熱量の違い
などが考えられる。
|