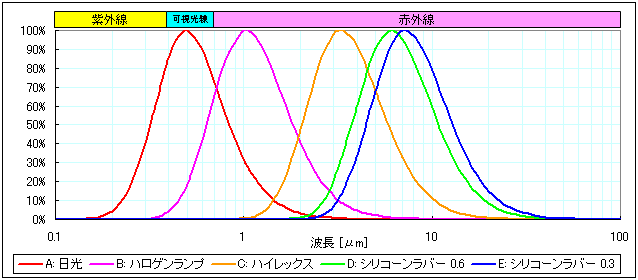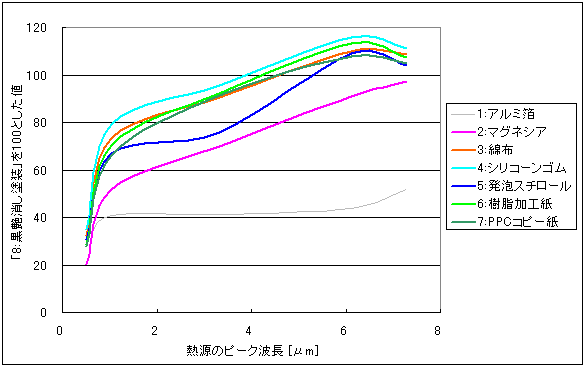LABORATORY熱の実験室
- 熱の実験室
- 元祖 熱の実験室
● 熱源のピーク波長と加熱特性 各熱源は、温度が異なりますので、放出する電磁波の波長が異なります。
ヒーターも含め、物体は、その持っているエネルギーを電磁波として放出します。その大きさと波長は温度によって変化して、黒体(表面に到達する放射エネルギーを全て吸収する物体)の場合、波長によるエネルギー:Eλは、Planck(プランク)の法則に従います。
この法則による計算値から、ピーク波長のときを 100%としたのが、下のグラフです。実際には、各物質は黒体ではありませんが、波長分布の傾向としてはこんな感じです。
ピーク波長は、温度が高いほど短くなり、Wien(ウィーン)の変位 則という、次の式に従います。
このピーク波長と、各物質の「8:黒艶消し塗装」を100とした加熱されやすさの関係を現したのが、次のグラフです。
日光の短い波長で加熱されにくいのは、1:アルミ箔も白い物質も同じですが、長い波長では、全く異なっていることが良くわかります。2:マグネシア以外の白い物質は、8:黒艶消し塗装より加熱されやすくなっています。
白い物質の中では、セラミックス材料の2:マグネシアは加熱されにくく、長波長での低下がありません。5:発泡スチロールは他とはカーブが異なっていて、中位の波長で低めになっています。 ● 実験の感想 可視光線を吸収しにくいので白く見える白い物質が、長波長の赤外線は吸収しやすいのではないか、と推測して実験を始めましたが、こんなに極端に差が現れるとは思っていませんでした。人間の目は可視光線の範囲しか見えないので、白は同じ白にしか見えませんが、赤外線でも波長の違いを色として感じることができるとしたら、全然違う色彩が見えると思います。白がいろいろな色に見えるのかも知れません。
|