● 走行したコース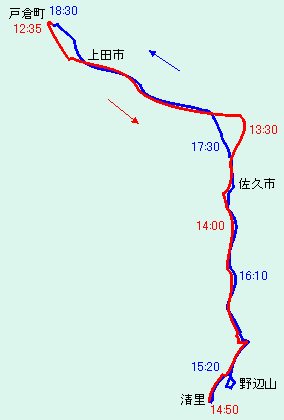
実験日は、2003年1月17日です。この日は気温が高めで、野辺山まで行っても寒さは期待できない感じでしたが、気温が高いのは野辺山だけでなく、まあ他に寒そうなところがないので、行ってみることにしました。快晴なので、放射冷却自体は確認できるはずです。
コースは右図のようになりました。赤が行きで、青が帰りです。赤字の時刻は行きの、青字の時刻は帰りの、大体の場所での通過時刻です。
野辺山の予定が、清里まで行ってしまいました。スタート時刻が早すぎたようで、野辺山ではまだ日も高かったので、もう少しすれば気温も多少は下がってくるかもしれないと思い、野辺山を素通りして清里まで行き、帰りに野辺山を回りました。
戸倉町の当社をスタート → 県道長野上田線で上田まで → 国道18号上田バイパス → 浅間サンラインで御代田町まで → 佐久IC近くをを通って国道141号線(佐久甲州街道)に入り、ひたすら清里まで
これが行きのルートで、帰りは多少違いますが、まあ似たようなものなので詳細は省略します。
走行距離は208kmで、燃費は14.9km/リットルでした。標高1,400m近くまで上ってはいますが、急な坂の区間は短いので、長い下り坂で燃費が稼げたようです。
● 全体の記録
走行した全体の温度変化は、次のグラフです。ずっと快晴でしたが、当然スタートから時間経過とともに日は傾いていき、17:00ちょうどくらいで日没です。
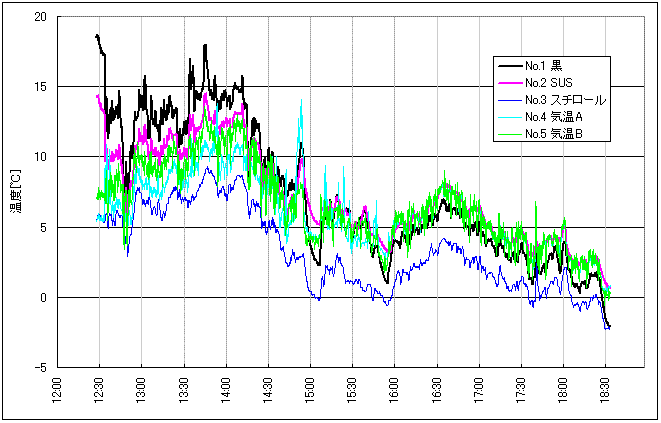
この実験で、温度を測定して比較しようとしたのは、No.1の黒いステンレス板と、No.2の光沢があるステンレス板でした。確かに、昼間は「No.1
黒」の温度が高く、日が傾くと「No.2 SUS」の方が高くなっています。でも、意外なのがNo.3の発泡スチロールの内部です。スタート直後のわずかな時間を除いて、常に一番低い温度になっています。
発泡スチロールは、2枚のステンレス板を熱的に浮かすために使ったつもりで、参考までに内部温度を測定しただけでした。それが、黒色つや消し塗装のステンレス板よりも、放射冷却の影響が大きくなっています。発泡スチロールに触れているのは、まわりの大気と2枚のステンレス板、簡易キャリアに固定するためのステンレスパイプですが、ステンレスパイプは温度測定箇所から離れているので、熱伝導が悪い発泡スチロールでは、まず関係ないはずです。大気もステンレス板も、発泡スチロールの温度より高いので、熱が発泡スチロールの表面から、赤外線として放出されているのでなければ、温度が下がりようがありません。素直に考えると、次のような理由だと推測されます。
- 発泡スチロールの表面の放射率は、波長によって大きく異なり、短波長域で低く、長波長域で高い。
- 太陽光線は、温度5780K(ケルビン)からエネルギーが放出され、ピーク波長は0.50μm。
- 5℃(278K)の発泡スチロールの温度では、ピーク波長は10.42μm。
- 短波長域で放射率が低いので、太陽からの放射熱エネルギーは吸収しにくい。
- 長波長域で放射率が高いので、エネルギーを赤外線として放出しやすい。
白い物質と言うのは、可視光線を吸収しにくいので白く見えるわけですが、波長の長い赤外線も同じように吸収しにくいわけではなくて、物質の種類により異なるようです。仮に、目が可視光線より長い波長だけ見えるとしたら、発泡スチロールは黒く見えることになります。
|

