LABORATORY熱の実験室
- ホーム
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
- 第7回 実験レポート
- 熱の実験室
- [熱コン]HAKKO熱の実験コンテスト
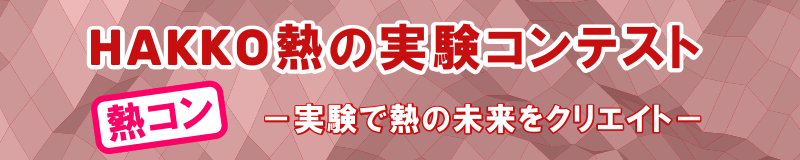
■ 「第7回 八光熱の実験コンテスト」 実験レポート
応募から選考された10チームに、第6回コンテストで継続進行になった1チームを加えた11チームの実験が、実験を実施しました。
| 連番 | 所属 (応募時点) | 実験メンバー (チーム名) |
| 実験タイトル | ||
| 実験レポート (説明は実験企画時の内容) | ||
| 所属50音順・敬称略 | ||
| 1 | 茨城大学 工学部 機械工学科 松村研究室 |
幸田 美沙紀、SAIFUL AKMAL、鈴木 敏修、 常盤 昭文、鷲山 博紀 |
| ドルフィンリングを作って遊ぼう! | ||
| ドルフィンリングが水中でドーナツ状のまま安定して存在する理由や、分裂・合体してもその形状を保つ理由は、まだほとんど解明されていない。水中で簡易にリングを作る装置を作成し、ドルフィンリングに関連する謎を解明したい。水温や空気の温度などを変化させることによって、ドルフィンリングがどのように影響を受けるのかを実験的に調べる。 | ||
| 2 | 宇部工業高等専門学校 機械工学科 機械材料研究室 |
小枝 達也 |
| 温度で駆動する人工筋肉素子の性能実験 ‐高齢者用ウェアラブル運動補助装置の開発を目指して‐ | ||
| 一般的なモーターを使用している運動補助装置では、重量、騒音、価格、寸法など種々の問題がある。高齢者が日常的に気軽に身につけることができる運動補助装置の実現を目指し、形状記憶合金(SMA)用いた人工筋肉素子(SMA人工筋肉素子)を使用して、加熱することで駆動する運動補助装置を作製し、その性能を評価し、実用化の可能性を検討する。 | ||
| 3 | 呉工業高等専門学校 専攻科 機械電気工学専攻 機械系 | 大久保 憲佑 |
| 熱電効果と自然エネルギーを用いて冷水を作れるだろうか? | ||
| 屋外でも冷却作用を持つ水筒があれば、飲料を詰め替えるだけで済むため、ペットボトル容器の消費を抑えることに繋がると考えた。太陽熱を熱電素子に集めて発電し、異なる金属を接合したものを用意して電流を流し、ペルチェ効果による金属接合部からの吸熱を利用して、容器内の流体を冷却する。 | ||
| 4 | 神戸市立工業高等専門学校 機械システム工学科 | 渡邊 紳之介、廣澤 謙弥、辻 翔大 (燃焼工学実験室 エンジンチーム) |
| ディーゼルエンジンによるクリーンな世界をめざして | ||
| ディーゼルエンジンは熱効率が高く、様々な燃料を用いられる可能性など、魅力的な特徴を持つ一方で、排ガスによる周辺環境への負担が大きい。様々な吸気条件での燃焼を試行することで、排ガス特性と燃焼特性にどのような影響がでるか調査する。そして、環境への負荷が少なく、かつ効率的な吸気条件を導くことを目的とする。 | ||
| 5 | 玉川大学大学院 工学研究科 機械工学専攻 熱エネルギー研究室 |
松下 将、足立 俊介、清水 龍希 |
| 太陽熱を使った熱交換器を作ろう!! | ||
| パラボラ鏡を用いて効率よく太陽光を集光・集熱し、蓄熱材に熱エネルギーを吸熱させ、温められた蓄熱材を利用して、外から取り入れた冷風を温風に変えるシステムを製作することを目的とする。効率よく実験を行うために、蓄熱材の結晶の連続生成実験と、太陽光の集熱実験の2種類を行う。 | ||
| 6 | 筑波大学 生命環境学群 生物資源学類 | 返町 洋祐 |
| 教材として利用可能な小スケール太陽熱発電装置の製作 | ||
| 太陽熱発電は、エネルギーの収集に使用される鏡が、太陽電池と比べ安価で頑強であるため、初期投資や運用コストが低減できると期待されているが、、国内における世間一般での知名度は決して高くない。そのため、教材に利用できるような、小型・安価・簡易的な構成の太陽熱発電装置の製作を目的とする。 | ||
| 7 | 東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 情報駆動制御研究室 |
波多野 隆馬、菅原 健、市川 貴仁、 山崎 智貴、宮木 直樹 |
| ドライアイスを用いたオルゴールの製作 | ||
| ドライアイスは、沸点が -79 ℃であり、金属を接触させると音が鳴るという面白い特性を持っている。この特性を利用してオルゴールを製作する。動力としては、現在注目されているペルチェ素子で発電した電力を用いる。ペルチェ素子を用いた発電方法の有効性を示すと共に、ドライアイスの新たな活用方法を見出すことを目的とする。 | ||
| 8 | 徳島大学 工学部 創成学習開発センター LED プロジェクト |
西村 信耶 |
| LED を用いた熱風における流速測定装置 | ||
| PIV particle image velocimetry(粒子像流速計)は、微粒子を分散させて、レーザーで照明し、照明されている流体をカメラで撮影して、その映像から速度と方向を求めるもので、非常にコストがかかる装置である。レーザーを LED に、超高性能カメラをデジタルカメラに置換した、ローコストの 3 次元 PIV を作成し、粒子を用い熱流速を計測する。 | ||
| 9 | 山梨大学 クリスタル科学研究センター | 久保田 恒喜、尹 儁赫、林 美月、亀井 章弘、 川村 翔、原 和生、平山 超也 |
| 熱障害で粘菌の行く手を阻めるか?? | ||
| 粘菌は、アメーバ状の細胞質の集団で移動して栄養を摂取し、熱や光を嫌う特性を持っている。また、粘菌が迷路の最短ルートを見つけ出すという性質が注目された。「熱を嫌う性質」 「迷路の最短ルートを見つけ出す性質」から、ルート選択が、熱によってどのように変化するのか、調べてみることにした。 | ||
| 10 | 山梨大学大学院 医学工学総合教育部 機械システム工学専攻 武田研究室 |
大橋 明生、望月 敬史、横山 大貴 |
| 太陽炉駆動スターリングエンジン船の製作 | ||
| 太陽の光エネルギーは、太陽光発電という形で利用されているが、太陽の熱エネルギーを有効に利用できているとは言えない。半球状の凹面鏡を利用し、太陽光を 1 点に集光することで高温の熱エネルギーが得られる「太陽炉」を用いて、これをスターリングエンジンの加熱源とし、その運動エネルギーによって船を動かすことを目的とする。 | ||
第6回コンテストから継続進行のチーム
| 11 | 茨城大学大学院 理工学研究科 機械工学専攻 神永・松村研究室 |
鈴木 博大、斎藤 光 |
| 熱を利用して土を使わず植物を育てよう! | ||
| 土壌栽培における気温管理は言うまでもなく行われていることであるが、地中にパイプを通して冷水や温水を流すことによって土壌内の温度管理も行い、作物を栽培する方法もあるように、水温を一定にして栽培したときの植物の成長度合いを観察し、水温を管理しない場合のものと比較することを目的とする。 | ||
