4. 計算結果および実験結果
今回実験に使用した熱板のサイズの値を代入して計算した結果と、実験結果を以下に示す。
物性値は膜温度の場合の値を採用した。
|
| 温度[℃] |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
| 水平(計算)[Wh] |
19 |
76 |
140 |
207 |
276 |
346 |
416 |
| 垂直(計算)[Wh] |
22 |
84 |
153 |
227 |
303 |
381 |
460 |
| 水平(実測)[Wh] |
20 |
70 |
150 |
240 |
340 |
450 |
580 |
| 垂直(実測)[Wh] |
20 |
90 |
180 |
270 |
360 |
490 |
630 |
表 2 計算結果と実測値
|
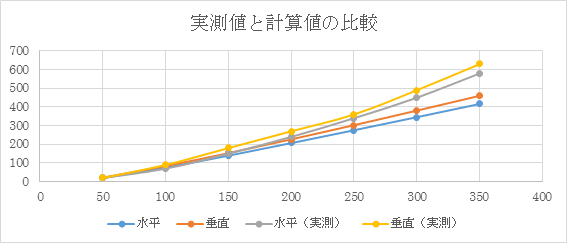
グラフ 1 実測値と計算値の比較 |
| 温度[℃] |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
| 垂直-水平(計算) |
3 |
8 |
14 |
20 |
27 |
35 |
44 |
| 差[%] |
14.5 |
10.7 |
9.8 |
9.7 |
9.8 |
10.2 |
10.5 |
| 垂直-水平(実測) |
0 |
20 |
30 |
30 |
20 |
40 |
50 |
| 差[%] |
0 |
28.6 |
20 |
12.5 |
5.9 |
8.9 |
8.6 |
表 3 水平と垂直の比較
|
5. 考察
垂直の方が水平に比べておよそ10%増しの放熱量となり、垂直の方が、放熱量が大きい結果となったが、予想よりもその差は大きくなかった。
計算値と実測値の差が、温度が上がるに従い増えているのは、熱損失の割合が、対流によるものと比較して、輻射によるものが大きくなったことが要因と考えられる。
今後の実験として、温度一定とした場合の各ヒーターの出力の比較や、1点制御した場合の温度分布を測定すれば、更におもしろい結果が得られるかもしれない。 |
|