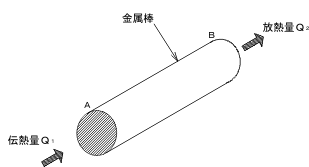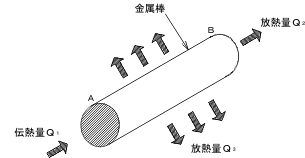熱の実験室-新館
第14回 熱エネルギー保存の法則を確かめる-1
新館は、4人の若手メンバーが交代で担当します
実験実施: 2008年10月
金属に熱を伝えると、伝えた点からの距離が長くなるに従い、金属の表面温度は低くなります。
これは、皆さんご存知の通り金属表面からの放熱によるものです。放熱とは物体表面から熱が放出されることを言い、その熱量は物体表面の放射率、外気への対流熱伝達率、物体表面の温度などにより計算できます。
ここで、以下の2つの場合について考えてみます。
| (1) 金属棒の側面を完全に断熱し、金属棒側面からの放熱を0とすると、A面からの伝熱量Q1とB面からの放熱量Q2の関係はどうなるでしょうか。 |
|
(2) 金属棒の側面は断熱せず、金属棒側面から放熱がある場合はどうなるでしょうか。 |
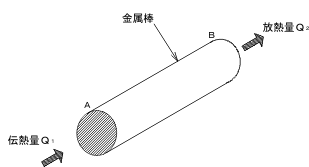 |
|
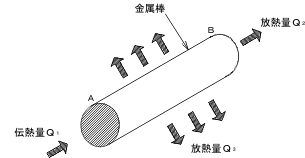 |
| 図. 金属棒(断熱あり) |
|
図. 金属棒(断熱なし) |
(1)の場合は、熱力学の第1則より、定常状態の場合は熱エネルギーが保存されるのでQ1=Q2となるでしょう。それでは、(2)の場合はどうなるでしょうか。Q1=Q2+Q3となるのでしょうか。実験をして確かめてみました。
● 使用するもの
- 熱板(温度調節器付き)
- Kタイプ熱電対
- φ10の金属棒(ステンレス、鉄、真鍮、アルミ)
● 実験方法
- 熱板に金属棒を差し込みます。
- 熱板の温度を100℃、150℃、200℃に保ちます。
- 熱板が各温度で安定したときの金属棒のB面の温度を測定します。
- 得られた数値から金属棒に伝わる伝熱量Q1、金属棒表面からの放熱量Q2、Q3を求め、Q1とQ2+Q3を比較してみます。
なお、用いる金属棒の熱伝導率、放射率は以下の値を使用します。
表. 金属棒の熱伝導率と放射率
| 材質 |
ステンレス |
鉄 |
真鍮 |
アルミ |
| 熱伝導率(W/m・K) |
16.7 |
50 |
99 |
230 |
| 放射率 |
0.85 |
0.3 |
|
● 実験結果
まず、最初に温度測定の結果を以下に示します。
表. 温度測定結果
| 熱板温度(℃) |
B面温度(℃) |
| ステンレス |
鉄 |
真鍮 |
アルミ |
| 100 |
72.5 |
87.5 |
90.2 |
93.3 |
| 150 |
101 |
126.4 |
133.7 |
137.7 |
| 200 |
130 |
165.3 |
175.8 |
182 |
|
次に、得られた温度を用いて、A面から金属棒に流れ込んだ伝熱量Q 1を求めます。その際、以下の式を使用しました。
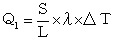 |
・・・ (1) |
|
| S:熱伝導する面積 |
|
L:棒材の長さ |
| λ:熱伝導率 |
|
ΔT:熱板との温度差 |
|
|
|
(1)の式より得られた、各材料の各温度での伝熱量を以下に示します。
表. 伝熱量計算結果
| 熱板温度(℃) |
伝熱量(W) |
| ステンレス |
鉄 |
真鍮 |
アルミ |
| 100 |
1.13 |
1.53 |
2.38 |
3.78 |
| 150 |
2.01 |
2.89 |
3.96 |
6.94 |
| 200 |
2.87 |
4.26 |
5.88 |
10.16 |
|
|